目次
物流KPIに関するよくある悩み
「物流のパフォーマンスを定量的に把握したい」
「課題を数字で捉えて、取るべきアクションを明確にしたい」
そう感じている企業は多いと思います。
しかし実際には、次のような壁に直面するケースが少なくありません。
- そもそも現場がアナログで、データが存在しない
- データを取る仕組みを作るにも、手間やコストが大きい
- 「何をKPIにすべきか」「どんな数字が改善につながるのか」がわからない
つまり、「測りたいけど、測れない」「測れても、活かせない」というのが、多くの現場での実情です。
物流は人手作業が多く、システム上で全てを可視化できるわけではありません。
だからこそ、「どのKPIを押さえればよいのか」を見極めることが、最初のステップになります。
物流KPIの具体例
ここで重要なのは、KPIを増やすことではなく、意味のあるKPIを選ぶことです。
実際に多くの企業を支援してきた中で感じるのは、
“本当に経営や現場改善に効くKPIは、実は多くない”ということです。
一例として、下図のような整理があります。
売上高対物流費のKPI分解イメージ
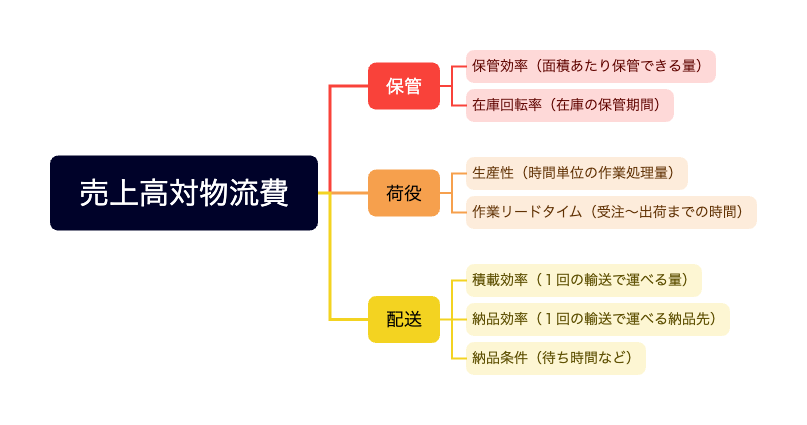
売上高対物流費を、保管・荷役・配送という3つの要素に分解。
各領域における代表的なKPI(効率・生産性・回転率など)を定義することで、
「どこに改善余地があるのか」を構造的に把握することができる。
このように整理することで、
- 保管効率が悪いのか(スペースの使い方の課題)
- 荷役生産性が低いのか(作業のやり方の課題)
- 配送効率が低いのか(積載やルートの課題)
といった改善の着眼点が自然と浮かび上がります。
つまり、KPIは「測るための数字」ではなく、「動きを決めるための数字」なのです。
まずは“意味のあるKPI”から始めよう
物流のKPIを考えるとき、いきなり完璧な指標体系を作る必要はありません。
最初は「一部の領域だけ」「手計測のデータだけ」でも構いません。
大事なのは、自社にとって“意味のある数字”を見極めることです。
KPIを選ぶということは、裏を返せば「改善の焦点を決める」ということ。
次回以降では、
今回紹介した保管・荷役・配送それぞれのKPIについて、
どんな数値をどう取ればよいのか、もう少し具体的に解説していきます。
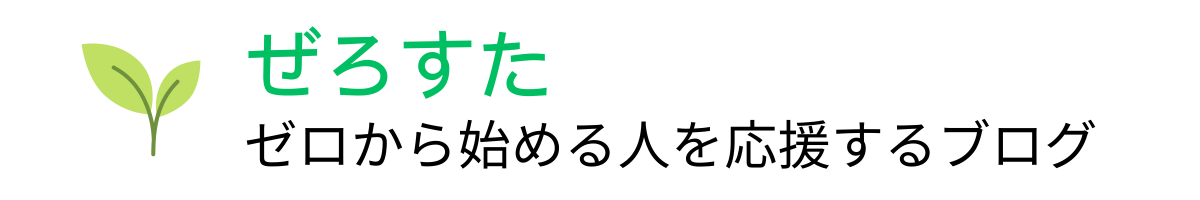


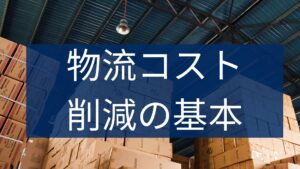



コメント