はじめに
どんな規模の企業でも、コスト削減は最も関心のあるテーマのひとつです。特に物流コストは、売上に直接影響するにもかかわらず「経営の盲点」になりやすい領域です。
実際に支援現場に入って感じるのは、物流コストを体系的に管理している企業は驚くほど少ないということ。商品1個あたりの物流コストを把握している会社はごくわずかで、せいぜい「売上高物流費(売上に占める物流費の割合)」をざっくり見ている程度。しかもそれを相場感と比較して「高いか安いか」を判断できていないケースがほとんどです。
物流コストは今後さらに上昇が避けられません。2024年問題(ドライバーの労働規制強化)、環境対応(脱炭素化への投資)、燃料費の高止まりなど、複数の要因が重なっています。「上がってきてから対策を打つ」では遅すぎるのです。
そこで本記事では、これまでの支援実績を踏まえて、物流コスト削減の3つの基本アプローチを解説します。
アプローチ1:現状の可視化
最初の一歩は、自社の物流コストをきちんと「見える化」することです。
物流コストが野放しになりがちな理由
人件費や原材料費と違い、物流コストは項目が多岐にわたり、社内で一元管理されていないことが多いからです。輸送費、保管費、荷役費、包装費…といった間接費がバラバラの部署で管理されており、全体像が見えていないのです。
そのため、「どの費用が大きく、どこに改善余地があるか」が把握できず、結果的に対策が後手に回ってしまいます。
可視化のステップ
- 物流費用の棚卸し
各拠点・各項目ごとのコストを整理。売上比だけでなく、商品1個あたりの物流コストを算出することが理想です。 - 相場との比較
同業種・同規模の平均と比べて、自社の水準が高いのか低いのかを判断します。 - 将来シナリオを描く
現状維持でいった場合、2024年問題や人件費上昇で将来どうなるかを試算してみる。これが「危機感」を生む第一歩になります。
可視化のポイントは、単なる集計にとどまらず「経営の意思決定に耐えうる粒度」でデータを持つことです。ここは専門的な知見が求められる部分でもあります。
アプローチ2:相場とかけ離れ、支出額の大きい項目を狙う
現状把握と相場比較ができたら、次は「どこに手を打つか」を絞り込みます。
優先すべき対象
- 相場との乖離が大きい項目
- 支出額そのものが大きい項目
この2つを同時に満たす部分が、最も投資対効果の高い改善対象となります。
単なる「安さ競争」に陥らない
かつては「より安い下請けを探す」ことでコスト削減を図るケースもありました。しかし昨今の物流業界は、人手不足や燃料費の高騰で「安さだけ」を追求するのは現実的ではありません。
むしろ大切なのは、中長期的に効率化を一緒に実現できる物流パートナーを見つけることです。物流は一朝一夕で改善できるものではなく、拠点設計やシステム連携など時間をかけて効率化していく領域だからです。
パートナー選びのために必要なこと
- どこに課題があるかを定量的に把握していること
- 改善に向けた方向性を自社として持っていること
これらを明確にすることで、物流会社との交渉も「価格だけ」ではなく「改善提案力」や「実行力」で評価できるようになります。
アプローチ3:各項目ごとの削減勘所を押さえる
最後に、物流コストを構成する主要項目ごとに「勘所」を整理します。
1.輸送費:最も大きな削減余地
輸送費は物流費全体の半分以上を占めることが多く、最も影響力の大きい項目です。
- 拠点ネットワークの最適化:配送先の重心を考慮して倉庫を配置する
- 輸送効率化:帰り便の活用、共同配送、効率ルートの設定
- 積載効率改善:荷姿の見直し、パレットの活用
- 納品条件の調整:毎日配送を週2回に変更するなど
2024年問題により輸送単価は上昇傾向にあります。その中で「積載効率を高める」「最短・最小ルートを組む」ことが生き残りのカギになります。
2.保管費:契約形態の見直し
保管費は、変動費型(使った分だけ支払う)と固定費型(坪建てで支払う)の2つが基本です。
- 波動が大きい商材は変動費契約が有利
- 一定量を扱う商材は固定費契約で単価を抑えるのが有利
また、保管場所によって相場は変動します。都心に近いと坪単価は高いが輸送費は下がる、地方は逆に保管費は安いが輸送費がかさむ。拠点配置の設計とセットで判断することが重要です。
3.荷役費:生産性の可視化がカギ
荷役費は「個数ベース」「人頭建て」など契約形態が多様です。重要なのは、商品1個あたりでどの程度コストが発生しているかを把握することです。
- 作業動線の改善や教育による生産性向上
- オープンブック方式(実際の人件費に基づき精算する)を採用し、双方で改善インセンティブを共有
こうした取り組みで、コスト削減と品質向上の両立が可能になります。
まとめ:仕組みとして定着させることが重要
物流コスト削減の3つの基本アプローチをまとめると以下のとおりです。
- 現状を可視化:商品1個あたりの物流コストを把握し、将来シナリオまで見据える
- 重点領域を特定:相場とかけ離れ、かつ支出が大きい項目を最優先で改善
- 各項目の勘所を押さえる:輸送・保管・荷役それぞれに適切な改善策を導入
繰り返しになりますが、重要なのは「一時的にコストを削る」のではなく、仕組みとして定着させることです。物流は経営の基盤であり、継続的な改善が企業の競争力につながります。
あなたの会社の物流コスト削減を一緒に考えませんか?
この記事で紹介したアプローチはあくまで基本です。実際には業種や取扱商品、取引条件によって最適な方法は異なります。
- 「自社の物流コスト構造を把握できていない」
- 「どの項目から手をつければいいのかわからない」
- 「物流会社との交渉を有利に進めたい」
そんな課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。実際のプロジェクト経験をもとに、貴社に最適な改善策をご提案します。
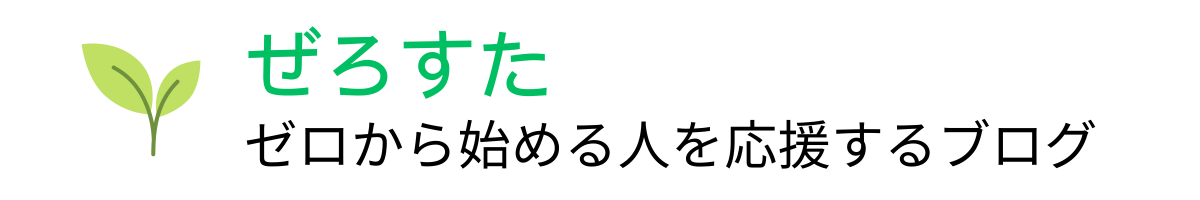

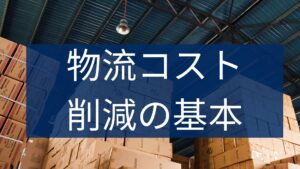




コメント