こんにちは。
コンサルタントを目指す学生の皆さんにとって、グループワーク面接は避けて通れない関門です。与えられた課題に対して複数人で議論し、限られた時間で結論を導くプロセスは、まさにコンサルタントの仕事そのもの。
巷には数多くの面接対策本があり、すでに基本的な知識やフレームワークを学んでいる方も多いでしょう。しかし実際の面接官の視点で「どういう行動が評価されやすいのか」を理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
就職活動において避けて通れないのが「グループワーク」。短時間で成果を出すことが求められるこの選考形式では、事前の準備と戦略が明暗を分けます。今回は、新卒としてグループワークに臨む際に意識したい3つのポイントを紹介します。
論理的に言えそうなことを発言する
コンサルタントの選考で最も重視されるのは「論理性」です。論理的であるとは、難しく言えば「インプットとアウトプットのつながりに納得感があること」、簡単に言えば「根拠に基づいて筋道立てて話せること」です。
まずは、与えられた情報をしっかりと読み取り、「この条件から言えることは何か?」を考えて発言しましょう。例えば、市場規模や売上推移が与えられていれば、その数値から導ける仮説を提示することが基本です。
さらに他の受験者と差をつけるには、一般常識や世の中のニュースを踏まえた発言が効果的です。たとえば「この業界は少子高齢化の影響を受けやすいから…」といった補足は、単なる与件整理を超えた広い視野を示すことにつながります。
グループワークで選ぶべき役割
多くの学生が迷うのが「自分はどの役割を担うべきか?」という点です。ここで覚えておいてほしいのは、基本的には普通のメンバーとして参加するのが最も有利だということです。
もちろん、議論を仕切る「ファシリテーター」や、議論を記録する「書記」といった役割もあります。経験があり得意な人なら挑戦してもよいですが、リスクも大きいことを理解しましょう。
- ファシリテーター
議論をリードする力や構造化する力を発揮できれば高評価につながります。ただし未経験の学生が無理に仕切ろうとすると、議論を空回りさせる危険もあります。 - 書記
一見「安全な役割」に思えますが、ただ板書しているだけでは評価されません。発言を構造化し、節目で「ここまでの議論をまとめると…」と整理できて初めて評価対象になります。メモを取りながら自分の意見を出すのは難易度が高く、トレーニングが必要です。 - メンバー
実は最もアピールしやすい立場です。無理に目立たなくても、発言の質や協働姿勢で十分評価されます。特に初めて挑戦する学生にはおすすめです。
多面的に物事を考える姿勢
グループワークの最大の落とし穴は、「自分たちの結論を盲信してしまうこと」です。制限時間がある中で、とにかく答えをまとめることを優先しすぎると、内容が浅く、幼稚な結論になりがちです。
そこで意識してほしいのが、「必ずポジティブ・ネガティブの両面からコメントする」という姿勢です。
たとえば「この施策を導入するとコスト削減効果が見込める」という議論が出たら、「一方で初期投資が必要になり、短期的には赤字になるリスクもあります」と補足する。これだけで、議論を深める人材として面接官の目に映ります。
さらに、「今回の時間内では十分に検討しきれなかった点」として論点を残しておくことも効果的です。これは「客観的に議論の限界を認識できる」姿勢を示し、視座の高さを印象づけられます。
実際のコンサルタントのプロジェクトでも同じです。提案は一度で完璧になることはなく、必ず内部やクライアントと議論を重ねてブラッシュアップしていきます。そのとき、自分の仮説の弱点を自覚し、論点として提示できる人材は重宝されます。
面接官が嫌うNG行動
ここまで「評価される行動」を解説しましたが、逆に「これをやると一気に減点される」という行動もあります。
グループワークでは、限られた時間内での振る舞いを見て、評価を行います。
そのため、発現量が少ないと判断要素が少なく、一部の発言だけで評価されてしまうリスクが高まります。何も思いつかない場合でも、他の人の発言の良いところと悪いところを適切な表現でまとめる、もしくはグループ全体のこれまでの議論ってこういうことだよね、って整理する。
そうすることで、自分だけでなく、他の人の認識もあっているか確認できます。
意識的に発言して、発現量では平均以上を目指しましょう。
グループワークで取り組んでいる意図の1つに、協調性の評価があります。
実際のプロジェクトでも1人で全て進めていくことはありません。必ずクライアントやコンサル側のメンバー・上司がいます。
そうした際に、みんなで議論して良い結論に導くことが不可欠になるため、協調性を持って建設的な議論をする必要があります。
絶対に自分の主張が正しい、というマインドは持たないようにしましょう。
これはあくまで言い方や振る舞いの話で、「自分はこういう根拠でこう思う。他の人はどうか?」と違う人の意見を求めるようにしましょう。
そうすることで、違った視点からのコメントを吸収して、あなた自身の仮説がより強固なものに発展していきます。
まとめ ― グループワークは「素養」を示す場
グループワーク面接は、正解を出すことが目的ではありません。大切なのは「与えられた情報をどう整理するか」「チームでどう議論を進めるか」「多面的に物事を捉えられるか」といった素養です。
一度コツを掴んでしまえば、どのファームの面接でも応用できます。さらに高評価を狙うなら、単なる論理展開だけでなく、自分の経験や斬新なアイディアを組み合わせた「本質的な仮説」を提示できると強い武器になります。
グループワークは試験であると同時に、自分の成長を試せる貴重な場でもあります。ぜひ今回紹介したポイントを意識して、挑戦してみてください。
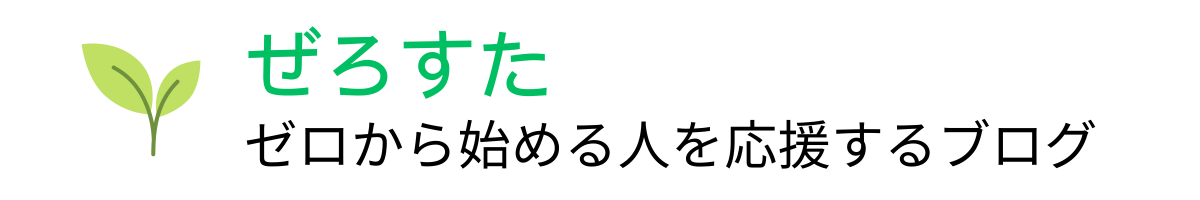

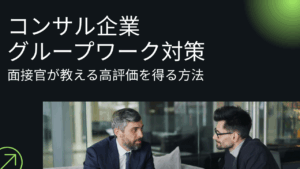

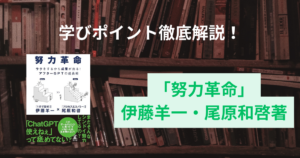
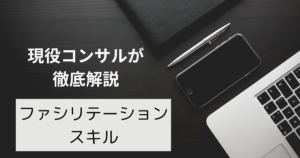
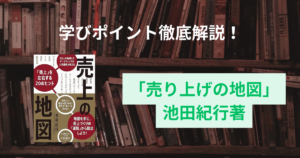
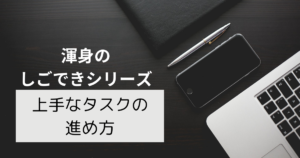
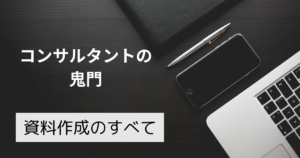
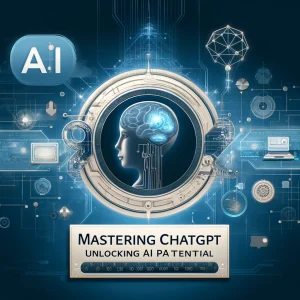
コメント