こんにちは。中小企業診断士のトキです。
今日は生成AIがテーマです。もはや、日常の仕事で使わない手はなくなったとも言える、生成AI。
皆さん、使ってますか?使いこなせてますか?
今日は、戦略コンサルタントがどのように日々の業務で生成AIを使っているか解説したいと想います!
はじめに
生成AIを使う人と使わない人では、生産性の差がすでに歴然です。
戦略コンサルタントとして日々クライアントの課題に向き合う中で、生成AIは「情報整理・戦略立案・資料作成」に欠かせない存在になりつつあります。
かつては、自分の経験やスキルに依存して考えざるを得なかった仕事が、いまやAIとの協働によって飛躍的にスピードと質を高められるようになりました。この記事では、現役コンサルタントの私が実際に行っている生成AIの活用法と注意点を紹介します。まだ生成AIを日常的に使っていないビジネスパーソンにとって、きっと参考になるはずです。
活用シーン① 戦略立案を加速する
戦略コンサルタントの仕事の多くは、「どの方向性で進めるべきか」を考えることです。
ただし参考にできる事例は、ある企業や業界特有の条件に依存しており、直接的には使えません。異なる業界では別の制約が働くため、一筋縄ではいかないのが実情です。
こうしたときに役立つのが生成AIです。
たとえば、次のように質問してみます。
- 「戦略の方向性を考えるうえで検討すべき論点は何か?」
- 「昨今のトレンドや外部環境の変化を踏まえると、◯◯業界・◯◯企業の課題や原因、解決策はどう整理できるか?」
すると生成AIは、網羅的な視点で論点を整理してくれます。通常なら専門家へのインタビューや資料調査に数日かかる作業が、わずか数分で完了するのです。
もちろん、そのまま答えを使うわけではありません。AIの提案を叩き台として人間が検証・補正することで、効率と品質の双方を高められます。
活用シーン② タスクの進め方を最適化する
多くのビジネスパーソンは、日々ルーティンや新規プロジェクトなど様々なタスクに追われています。
「この進め方でいいのだろうか?」「もっと効率的な方法はないか?」と迷ったことはないでしょうか。
生成AIは、タスクの進め方を評価・改善するパートナーにもなります。
たとえば、「新しい業務プロセスを導入する際のステップを整理して」と入力すれば、幅広い視点で進め方を提案してくれます。
そこから自分の現場に合わせて修正すれば、ゼロから方法論を考えるより圧倒的に早く、しかも抜け漏れが少なくなります。
実際、私自身も「会議準備の段取り」「調査タスクの切り分け」などをAIに相談し、作業効率を20〜30%改善できました。
今後は「生成AIでたたき台を作り、人間が仕上げる」という流れが、仕事のスタンダードになるでしょう。
活用シーン③ 資料作成を爆速化する
ビジネスパーソンにとって避けて通れないのが資料作成です。
構成を考え、分かりやすいメッセージに落とし込み、表現を整える。この作業に多くの時間を取られている人は少なくありません。
生成AIはこの領域でも強力なサポートを発揮します。
- 「このテーマを伝えるための最適な構成は?」
- 「意思決定者に響くメッセージを3案考えて」
- 「専門用語を使わずに説明するとどうなるか?」
こうした問いに対して、多様な視点からアイデアを提示してくれます。さらに最近はWeb検索機能を持つAIも登場しており、最新トレンドを反映した提案も可能です。
結果として、従来なら数時間かかっていたスライド作成が1〜2時間に短縮されることも珍しくありません。
注意点:過信せず「育てる」姿勢が重要
ここまで紹介した通り、生成AIは強力なツールですが、注意点もあります。
- 誤回答リスク
AIは時にもっともらしいが誤った情報を返すことがあります。正解を与えてくれる存在ではなく、「一緒に考えるパートナー」として扱うべきです。 - 指示の精度が成果を左右する
あいまいな問いを投げれば、あいまいな答えしか返ってきません。プロンプト(指示文)の精度を上げることが成果の鍵です。 - アウトプットの鵜呑み禁止
生成AIが返す文章や分析を、そのままクライアントや上司に提出するのは危険です。人間の視点で検証し、修正を加えるプロセスは必須です。 - セキュリティと倫理の配慮
企業秘密や個人情報を入力することは避けるべきです。利用規約やデータの取り扱いについても十分理解しておく必要があります。
生成AIは「即戦力」ではなく「成長させるツール」。この視点を持つことで、リスクを避けつつ最大限の価値を引き出せます。
終わりに
生成AIはもはや一部の先進的な人だけが使うツールではありません。
戦略立案、タスク管理、資料作成など、あらゆる場面で活用できる「第二の頭脳」として、ビジネスの現場に浸透しつつあります。
大切なのは、「AIに任せる」のではなく「AIと協働する」姿勢です。
小さな業務から取り入れることで、その効果を実感できるはずです。
明日の資料作成から、ぜひ生成AIを試してみてください。
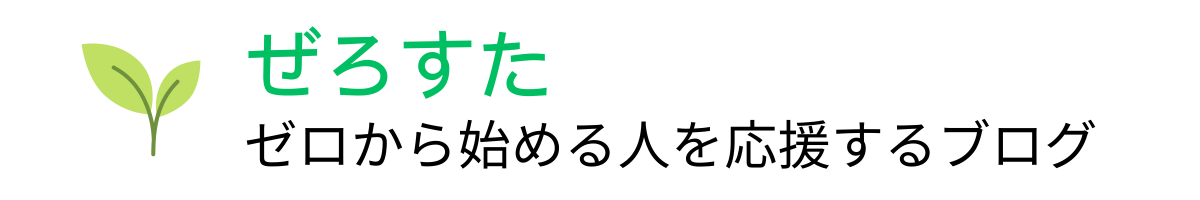


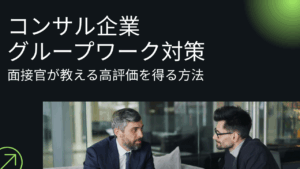
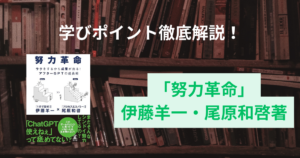
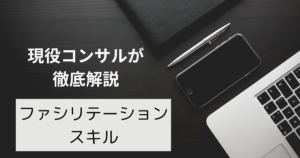
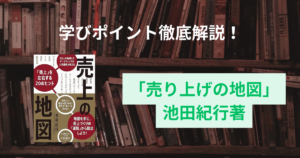
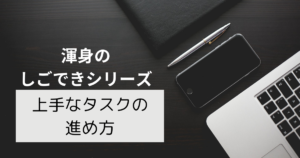
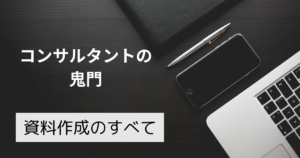
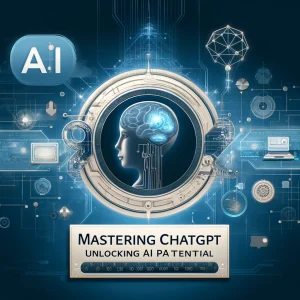
コメント